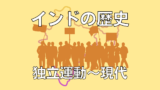中東でイスラム教が誕生し、その後にアフリカやアジアでイスラム教国家ができました。これらの地域を「イスラム世界」と呼びます。今回はイスラム世界の歴史については3つ目、インドの歴史の中では2つ目の記事です!
今回はインドのイスラム王朝について話していきます。
古代インドの歴史はインダス文明から始まり、その後、マウリヤ朝→クシャーナ朝→グプタ朝→ヴァルダナ朝と続きました。ヴァルダナ朝が滅んだ後、インドは再び小さな国々に分かれて争いが続きました。
詳細はこちらです。

その後、アフガニスタンにガズナ朝→ゴール朝が現れ、インドに侵入し、そのさいに北インドにイスラム教がひろがりました。その後、インドにはデリー=スルタン朝→ムガル帝国というイスラム王朝が興りました。
インドに侵入したイスラム王朝・ガズナ朝とゴール朝
中央アジアのサーマーン朝から独立して、アフガニスタンにイスラム王朝のガズナ朝(962~1186)ができました。この国は北インドへの略奪をくり返しました。
ガズナ朝をたおしてアフガニスタンを支配したゴール朝(1148頃~1215)も、北インドへの侵入をつづけ、寺院の破壊やイスラム教の布教をしました。この侵入により北インドのイスラーム化が進みました。
デリー=スルタン朝…デリーが都の5王朝
ゴール朝の末期、インド最初のイスラーム王朝デリー=スルタン朝(1206~1526)が生まれました。
デリー=スルタン朝はデリーを都とする5つの王朝をまとめた呼び名で、順に奴隷王朝→ハルジー朝→トゥグルク朝→サイイド朝→ロディー朝と続きます。
奴隷王朝(1206~1290)は、建国者のアイバクがもともとゴール朝の奴隷だったため、こう呼ばれました。
奴隷王朝の時代に、インドで一番古いイスラーム教寺院のクトゥブ=ミナールが建てられました。
南インドの王朝
同時期の南インドでは
- (後期)チョーラ朝(9~13世紀)
- ヴィジャヤナガル王国(1336~1649)
などの国がありました。
インド=イスラーム文化
デリー=スルタン朝からムガル帝国時代のインドで特徴的なのがインド=イスラーム文化です。
デリー=スルタン朝の時代に、インドのヒンドゥー教文化がイスラームと融合して、インド=イスラーム文化という新しい文化が生まれました。それがムガル帝国の時代に発展していきました。
インド=イスラーム文化の代表的な産物として
- イランから伝わった技術を取り入れ、ムガル帝国の宮廷で栄えた細密画(ミニアチュール)
- ムガル帝国時代に建てられたタージ=マハル
- イスラム教とヒンドゥー教が融合したシク教
- イスラム王朝であるムガル帝国の支配者が使用したペルシア語とインドの言葉が混ざったウルドゥー語
などがあります
ムガル帝国で使われた言語
ムガル帝国に関係する主な言語を紹介します。
- ヒンディー語:古代インドのサンスクリット語から派生した言語で、北インドのデリーなどで使用されていました。イギリスの支配時代には、ヒンドゥー教徒の標準語として普及し、現在のインドでは公用語の一つとなっています。
- ペルシア語:ムガル帝国の宮廷や支配者層、そしてムガル帝国の隣にあったサファヴィー朝が使用していた言語。ムガル帝国の公用語として広く使用されていました。
- ウルドゥー語:ムガル帝国時代に生まれた言語であり、北インドの言語の文法とペルシア語・アラビア語の単語が融合したものです。現在ではパキスタンの公用語となっています。
シク教の創設
16世紀初頭、インドでイスラーム神秘主義とヒンドゥー教を融合させたシク教がうまれました。
教祖はナーナクという人です。
今ではキリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教についで、世界で5番目に信者の多い宗教となっています。
ムガル帝国の皇帝たち
デリー=スルタン朝のあと、インドではムガル帝国が栄えます。
バーブルとアクバル
ムガル帝国(1526~1858)の建国者バーブルはイランのティムールの子孫です。デリー=スルタン朝の最後の王朝であるロディー朝をたおし、イスラム国家のムガル帝国を建国しました。国名の「ムガル」は「モンゴル」からきた言葉です。
1556年にアクバルが3代目の皇帝になって、ムガル帝国は全盛期を迎えます。
アクバルは
- 都をアグラに移しました。
- マンサブダール制という官僚制度を整えました。官僚たちをランク分けし、ランクに応じて給料などを決めました。
- 非イスラーム教徒にかけていた人頭税(ジズヤ)を廃止し、イスラーム教徒以外にも寛容な態度をとりました。
ただ、ここでおこなった人頭税の廃止が後で裏目に出てしまいます。
タージ=マハル

17世紀前半の皇帝シャー=ジャハーンは都のアグラに、王妃のお墓であるタージ=マハルをつくりました。これはインド=イスラーム建築の代表的な建造物として知られています。
しかし、タージマハルの建築には莫大な費用がかかりました。さらに、以前にアクバルが人頭税を廃止していたために、ムガル帝国は財政難となってしまいました。
.png)
アウラングゼーブ
17世紀後半、シャー=ジャハーンの後をついだアウラングゼーブは財政難を解決するために非イスラーム教徒に対する人頭税(ジズヤ)を復活させました。
また、対外遠征を行い、デカン高原を征服してムガル帝国の領土を最大にしました。
しかし、人頭税(ジズヤ)の復活は非イスラーム教徒たちの反発を招きました。
各地で反乱がおき、マラーター王国、シク教徒たちなどが、実質的に独立状態になりました。

増税反対!!!
ムガル帝国はこの時期まで全盛期でしたが、1707年にアウラングゼーブがなくなった後、急速に衰退していきました。
ムガル帝国の滅亡
シャー=ジャハーンの時代から、ヨーロッパ諸国のインド進出が始まり、イギリス東インド会社とフランス東インド会社の商館がインドにおかれました。
18世紀中ごろになると、イギリスによるインドの植民地支配が本格化しました。
イギリス東インド会社は、1765年にインド東部のベンガル地域などでの徴税権を得ました。
さらにイギリス東インド会社は
- 1767年に始まったマイソール戦争
- 1775年に始まったマラーター戦争
- 1799年に始まったシク戦争
に勝利し、インドのほぼ全域を支配下におさめました。
このころムガル帝国の領土は、デリー周辺だけのかなり小さいものになっていました。
この時期、ムガル帝国の領土はかなり小さくなり、主にデリー周辺だけになっていました。
インド大反乱(シパーヒーの反乱)

1857年からインドで起きた、イギリス東インド会社の支配への反乱をインド大反乱(シパーヒーの反乱)といいます。
シパーヒーというのは、東インド会社に雇われたインド人傭兵たちのことです。彼らはデリー城を占拠し、インドのムガル皇帝を擁立して反乱を起こしました。この反乱に民衆も参加し、全インドにわたる大規模な反乱になりました。
しかし反乱は鎮圧され、ムガル帝国は名実ともに滅亡しました。
イギリスは直接的な支配を開始し、1877年にインド帝国を成立させました。
初代インド皇帝にはイギリスのヴィクトリア女王が即位しました。
おわりに
インド方面ではガズナ朝 → ゴール朝 → デリー=スルタン朝 →ムガル帝国のイスラム王朝が栄え、インド=イスラーム文化が発展しました。
しかし1877年にインド帝国がつくられ、イギリスの植民地となりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
▼この後のインドの歴史についてはこちら